ここから本文です。
アート・コレクション
小林萬吾ー師に学び、歩んだ道
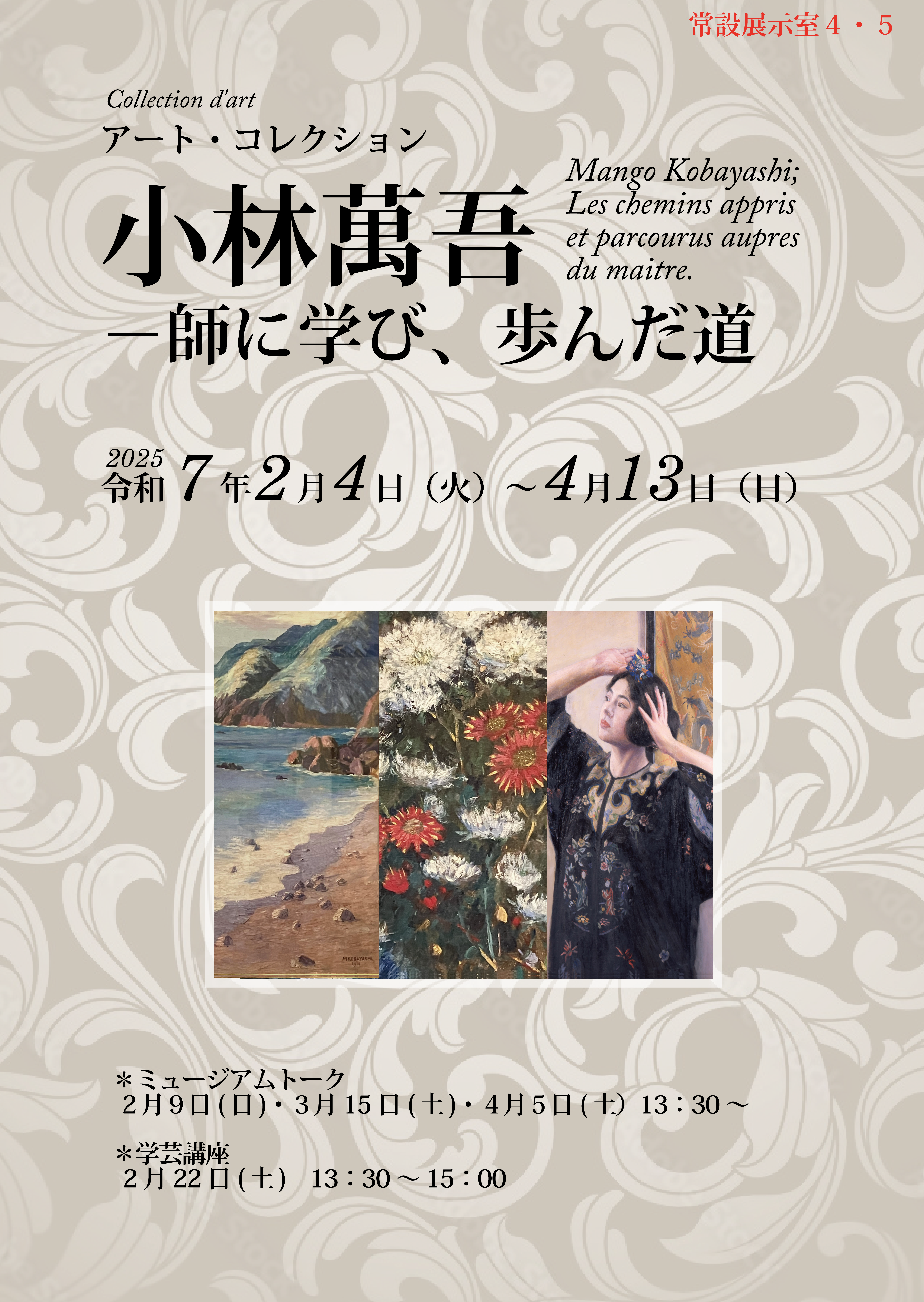
展示の概要
55年ぶりに再発見の作品も展示!
- 香川県三豊市詫間町出身の画家小林萬吾(1868-1947)は、日本洋画の父・黒田清輝(1866-1924)に学び、明治時代から終戦直後まで活躍しました。令和6年(2024)は黒田清輝没後100年であり、これを機に、師であった黒田清輝との関わりを振り返りつつ、小林萬吾の作品を紹介します。
- また、本展は、小林萬吾の生前時にゆかりのあった家々で受け継がれてきた作品や55年ぶりに再発見された作品など、香川県内各所で所蔵される貴重な作品を中心にご覧いただきます。
| 会期 | 令和7年2月4日(火曜日)から令和7年4月13日(日曜日) |
| 開館時間 |
午前9時から午後5時
|
| 休館日 |
毎週月曜日(2月24日(月曜日・振替休日)は開館)、 2月25日(火曜日)、 3月4日(火曜日)から3月9日(日曜日) |
|
会場 |
香川県立ミュージアム(高松市玉藻町5-5)常設展示室4・5 |
| 展示数 | 27件27点 |
| 観覧料 |
一般410円、団体(20名以上)330円
|
関連イベント
ミュージアムトーク
展示内容について担当学芸員がわかりやすくお話しします(申込み不要)
| 日時 |
令和7年2月9日(日曜日)、3月15日(土曜日)、4月5日(土曜日)
|
| 会場 | 常設展示室4・5 |
| 参加料 | 無料(別途観覧券が必要) |
| 申込 | 不要 |
学芸講座「小林萬吾ー師に学び、歩んだ道」
黒田清輝や仲間たちとの交流やその中で育まれた画業、郷土香川の関わりなどから、小林萬吾の足跡をわかりやすくお話しします。
| 日時 |
令和7年2月22日(土曜日)午後1時30分から午後3時(会場は午後1時)
|
| 会場 | 研修室(地下1階) |
| 参加料 | 無料(別途観覧券が必要) |
| 申込 | 電話(087-822-0247)、または香川県電子申請届出システム(外部サイトへリンク) |
展示品
| 小林萬吾「赤布を纏える女」 | |
|---|---|
|
大正6年(1917)、第11回文展出品作(1917)、個人蔵
|
|
|
|
|
| 小林萬吾「花鈿」 | |
|
昭和2年(1927)、第8回帝展出品作(1927)、当館蔵
|
|
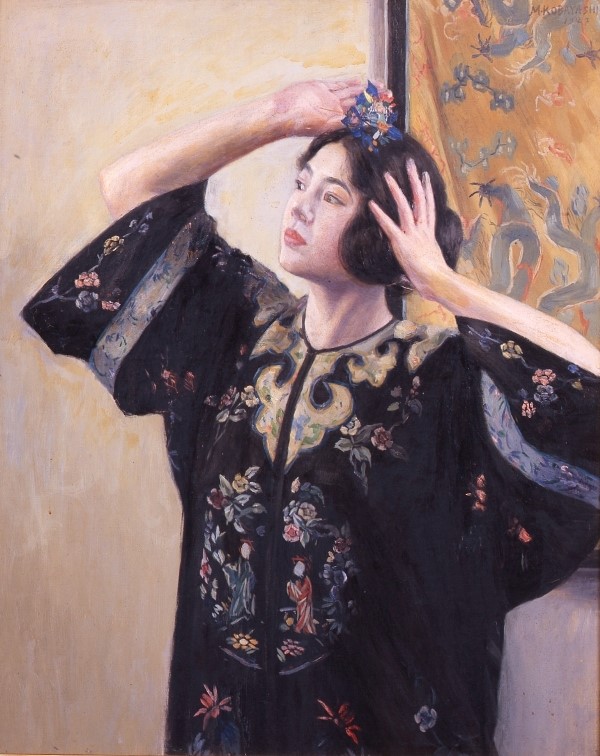 |
|
| 小林萬吾「蔦島公園」 | |
|
制作年不詳、個人蔵
|
|
 |
このページに関するお問い合わせ
