ここから本文です。
総量削減計画
第9次総量削減計画について
令和4年11月2日付けで水質汚濁防止法の規定に基づき、総量削減計画を策定するとともに、同計画に基づく総量規制基準を設定しましたので、お知らせします。同計画に基づき、総合的・計画的に汚濁負荷量の削減を進めて参ります。
なお、総量規制基準については、第8次規制から変更ありません。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
水質総量規制制度について
1.経緯
水質総量規制制度は、昭和53年に水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法の改正により導入されており、人口、産業等が集中し汚濁が著しい広域的な閉鎖性水域について、生活環境保全に係る水質環境基準の確保を目的として、当該水域の水質に影響を及ぼす地域から発生する汚濁負荷量の総量を一定量以下に削減しようとする制度です。
これまで、東京湾、伊勢湾、および瀬戸内海において、昭和54年から化学的酸素要求量(COD)を対象に、また、第5次からは窒素含有量及びりん含有量を新たな対象項目に加え実施されています。
2.制度の特徴
- (1)都府県毎に知事が定めた総量削減計画に基づき、計画的に汚濁負荷量を削減する。
- (2)排水の規制は濃度ではなく、汚濁負荷量(排水濃度×排水量)で規制(総量規制基準)する。
- (3)規制のみでなく、下水道の整備等の事業の実施、小規模事業場に対する指導の実施等の施策を総合的に推進する。
- (4)東京湾、伊勢湾、および瀬戸内海に面した地域のみならず、その水域に関係する内陸部も対象とする。
対象水域、対象地域
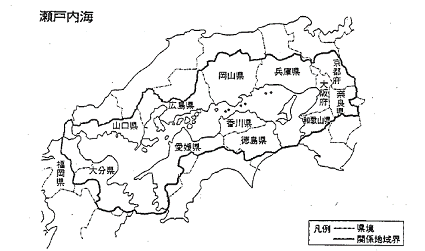 対象水域、対象地域対象水域である瀬戸内海とは、いわゆる常識的な意味での瀬戸内海のほか、この海域と一体的に環境の保全を図る必要がある海域として、豊後水道及び響灘の一部が含まれています。
対象水域、対象地域対象水域である瀬戸内海とは、いわゆる常識的な意味での瀬戸内海のほか、この海域と一体的に環境の保全を図る必要がある海域として、豊後水道及び響灘の一部が含まれています。
また、対象地域は内陸府県である京都府、奈良県を含む2府11県から成り、香川県は全域が指定地域に定められています。
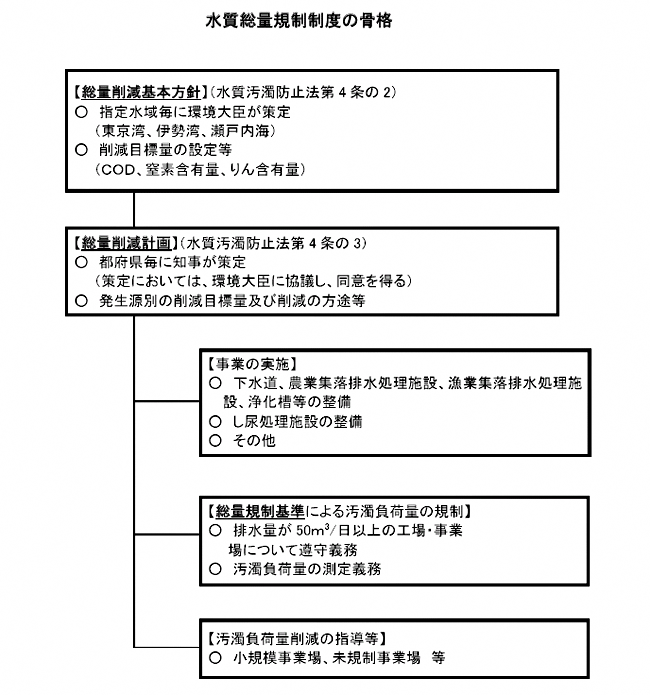
このページに関するお問い合わせ